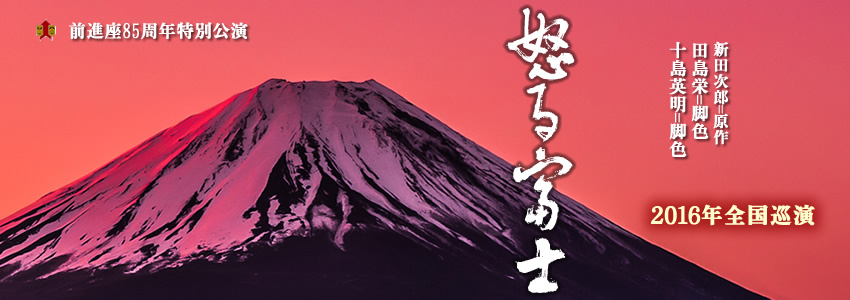-
五代将軍綱吉の世。宝永4(1707)年11月23日(旧暦)、富士が火を噴いた。山麓の村々は焼け砂に埋まり、田畑は壊滅したのである。幕府は急遽、関東郡代・伊奈半左衛門に被災地代官を命じた。だが、幕閣たちは醜い派閥抗争に明け暮れていた。
ある日、半左衛門の陣屋に深沢村の若者・佐太郎、こと ら4人が訪れた。彼らは命がけで村を出て来たのであった。「食する物は何もなく、鳥さえも去っていった・・・・・・」半左衛門は被災地に急行し農民を励ます。「お上は決して民を見捨てはしない―」と。
だが幕府の裁定は亡所というものであり、村々では飢えに倒れる者や故郷を捨てる者が相次ぐ。
将軍が代わり実権は柳沢吉保から間部越前守に移るが、誰一人として富士山麓に目を向けようとはしなかった。半左衛門は己の命を懸けて公儀に異を唱える決心をする。そして、その義心に心動かされた駿府代官は・・・・・・



富士山の火山活動は3つの時代に分けられます。
一番古い小御岳(こみたけ)火山は、今の富士山の場所で10万年以上前に活動していました。その次に古富士火山が8万年前頃から爆発的な噴火を繰り返して大きな山体を形成しました。その後1万年前から現在の新富士火山の活動に移行したのです。
新富士火山の噴火では、大量の火山灰や火山弾などの降下噴出物、溶岩、火砕流などの流出が特徴です。平安時代は特に火山活動が活発で、800~8002年(延暦19~21年)に大量の火山灰を降らせたと「日本後紀」に記載された〝延暦の大噴火〟があり、864年には山腹から大量の溶岩を流出し現在の青木が原樹海の元を形成した〝貞観の大噴火〟がありました。
〝宝永の大噴火〟とこの2回の大きな噴火をあわせて、歴史時代の富士山三大噴火と称されるそうです。

噴火からさかのぼること4年、1703(元禄16)年12月、南関東地方に〝元禄大地震〟発生、大きな被害を出しました。このときの影響からか、年末から年始にかけて富士山に鳴動がありました。
噴火の始まる49日前の10月28日には、日本最大級の地震(推定マグニチュード8.6)といわれる〝宝永地震〟が起こります。この地震は、定期的に巨大地震を起こしている2箇所の震源域、すなわち遠州沖を震源とする東海地震と紀伊半島沖を震源とする南海地震が同時に発生したと考えられています。
地震の被害は東海道、紀伊半島、四国におよびました。
そして1707(宝永4)年12月16日午前10時頃、南東斜面から大噴火します。噴火は1月1日未明まで断続的に続き、噴出した火山礫や火山灰などの噴出物は、偏西風にのって現在の静岡県北東部から神奈川県北西部、東京都、さらに100㎞以上離れた房総半島にまで降り注ぎました。最大3mに達する〝焼け砂〟に覆われた現御殿場市から小山町(御厨地方)は、家屋や倉庫が倒壊または焼失し食料の蓄えはなくなり、田畑は耕作不可能に、用水路も埋まって水の供給も絶たれ、深刻な飢饉に陥りました。
また、雨のたびに河川に火山灰が流れ込んで河床を上げていましたが、噴火の翌年1708(宝永5)年8月、大雨によって大量の火山灰が酒匂川に流入し、足柄平野の入口に設けられていた大口堤が決壊、下流の村々が土石流で埋め尽くされました。
その後も復旧するたびに堤が切れ村々が土砂に埋まるという二次災害が続き、これらの田畑の復旧にも長い時間を要しました。-

江戸時代中期の関東郡代。関東郡代とは関八州の幕府直轄領の民治を司る地方官であり、行政・裁判・年貢徴収なども取り仕切り、警察権も統括していました。徳川家康の関東入府の際に伊奈忠次を関東の代官頭に任じたことに始まり、その後12代200年に渡って伊奈氏が世襲したのです。 忠順は、代官頭の時代を含めると七代目。夭逝した兄忠篤の養子となって、関東郡代職と武蔵野国赤山(現埼玉県川口市赤山)四千石の赤山陣屋の遺領を継ぎ、幕府代官として架橋工事、治水工事を主に行ないました。
1707(宝永4)年12月に発生した富士山の噴火に際し、砂除川浚(すなよけかわざらい)奉行と呼ばれる災害対策の最高責任者に任じられ、主に川底に火山灰が堆積していた酒匂川の砂除けや堤防修復などに従事。しかし、当時もっとも被害のひどかった駿東郡御厨地方へは幕府の支援が一切行なわれず、59ヶ村が「亡所」とされ放棄されたのです。忠順は、飢餓に苦しむ者が続出する悲惨な状況に見て見ぬ振りができず、独断で駿府紺屋町の幕府の米倉を開き、1万3千石を村々の領民へ分配しましたが、結果的にこの無断行為を咎められ罷免、切腹を命じられたのです。
忠順の救済により救われた農民たちは、その遺徳を偲び1867(慶応3)年に祠を建て、その後須走村(現静岡県駿東郡小山町須走)に伊奈神社を建立しその菩提を弔いました。
-

噴火が起こったのは「生類憐みの令」で有名な徳川綱吉の治世(1680~1709年)末期の1707(宝永4)年。江戸や上方の大都市では元禄文化と呼ばれる町人文化が発展していた。噴火の前年には、1702(元禄15)年に起こった赤穂浪士の討ち入り事件が、近松門左衛門の筆で人形浄瑠璃として初演されています。
降灰の多かった地域の大部分は小田原藩領でしたが、藩は緊急の救恤米を支給したのみで、後は幕府に返上、対策を委ねざるをえませんでした。幕府は半左衛門を災害対策の責任者に任命。また、全国の大名領や天領に対し強制的な献金(石高100石に対し金2両)の拠出を命じ、被災地救済の財源としました。しかし、集められた40万両のうち被災地救済に当てられたのはわずか16両で、残りは逼迫していた幕府の財政に流用。この地方は「亡所(=収税地と見なさない替わりに手当てもしない土地)」とされたのです。
噴火の翌々年(宝永6年)1月、五代将軍綱吉が逝去。綱吉の寵愛篤かった柳沢吉保から、新将軍徳川家宣とその儒者新井白石に権勢は移りましたが、幕府の要職は災害までも材料にして権力争いに明け暮れるありさま。
結局、復興により幕府から元の所領の小田原藩に返されたのは、噴火から実に36年後のことでした。